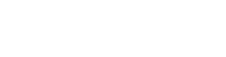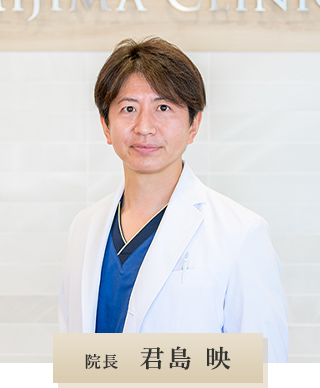大腸がんとは
大腸がんは、大腸から発生するがんの総称です。
現在、日本人の年間罹患者数は14万人を超え、男女を合わせると全てのがんの中で第1位となっています。また、年間死亡者数も5万3000人以上で、全てのがんの中で第2位を占めています。
大腸がんの発生には、生活習慣が深く関わっていることが知られており、喫煙、飲酒、肥満、肉食の欧米型食生活、家族歴などが危険性を高める要因とされています。
近年では、50歳未満の若年層における大腸がんの増加が非常に大きな問題となっており、日本では大腸がん患者の罹患数は継続して増加しています。
最近の疫学研究では、日本は世界の中でも欧米諸国を抜き、50歳未満で世界第5位、50歳以上で世界第3位とトップクラスの罹患率であり、若年層の患者も年々増加しています。現在、日本では欧米と比較して急増しているこの原因の解明が強く求められています。
大腸がんの発生経路は主に3つあります。
- 腺腫-癌シークエンス: 大腸にできるポリープ(腺腫)が時間をかけて徐々にがん化していく経路で、大腸がんのほとんどがこの経路をたどると考えられています。
- de novo(デ・ノボ): ポリープを経由せず、正常な粘膜から直接がん化するタイプで、比較的進行が早いとされます。
- 鋸歯状病変からの癌化: 以前はがん化の可能性が低いとされていた鋸歯状病変から進行するがんで、近年増加傾向にあると言われています。
大腸がんの症状
大腸がんは、早期の段階ではこれといった自覚症状がほぼありません。肛門に近い場所にできたごく一部のがんで、たまたま血便が出ることがありますが、基本的には症状がないと考えておいた方がいいでしょう。
痔の出血や、なんとなく便秘や下痢が続くなと思っていたら、偶然健康診断の便潜血検査で発見されるケースが多いのはそのためです。症状が出てから見つかることは少ないので、きっかけがないと気づくのが難しいがんです。
がんが進行すると、以下のようなさまざまな症状が現れることがあります。
〇便に血が混じる(血便): 肛門に近い場所からの出血だと、鮮やかな赤い血が混ざります。一方、大腸の右側から出血した場合は、腸内で血液が酸化されて色が変わり、黒っぽい便や暗赤色の便になることがあります。
〇便の形や太さが変わる: 便が細くなったり、硬くなったりします。
〇便秘や下痢になる、便の状態が不安定になる
〇残便感がある: 便を出したのに、まだ残っているような感じがします。これは、肛門に近い直腸やS状結腸にがんがある場合によく見られます。
〇腹痛: がんが進行して腸が狭まり、便が詰まりそうになっているときに、腹痛が起こることがあります。これを腸閉塞といいます。
〇体重減少: 転移するほど進行している場合、がん細胞が栄養を奪うため、栄養失調になり、体重が減ることがあります。
〇貧血: 慢性的に貧血になることで、大腸がんが見つかることもあります。
大腸がんのステージ
大腸がんのステージは、0から4までの5段階でがんの進行度を表します。ステージを決定する要素は以下の3つです。
- 深達度(しんたつど): がんがどれくらい大腸の壁に深く入り込んでいるか。
- リンパ節転移: 腸の周りのリンパ節や、大腸から離れたリンパ節に転移しているかどうか。
- 遠隔転移: 肝臓、肺、腹膜などの大腸周囲のリンパ節以外の臓器に転移しているかどうか。
各ステージの概要は以下の通りです。
ステージ0: 大腸の粘膜の非常に表面にとどまっているがん。
ステージ1: リンパ節や他の臓器への遠隔転移がなく、固有筋層(大腸の筋肉の層)までにとどまっているもの。
ステージ2: 固有筋層を超えて大腸の外まで広がっているが、リンパ節への転移がないもの。
ステージ3: がんの深さは関係なく、リンパ節に転移があるもの。
ステージ4: がんの大きさやリンパ節転移に関係なく、遠隔転移(肝臓、肺、腹膜などへの転移)をしているもの。
大腸がんの原因
大腸がんの原因は、大腸粘膜が何らかの要因によって慢性的に刺激を受け、遺伝子レベルでのダメージ(障害)を受けることによってがん化するとされています。しかし、未だ完全な原因は解明されていません。
主なリスク要因として、生活習慣(喫煙、飲酒、肥満、肉食の欧米型食生活)や家族歴が挙げられます。
大腸がんになりやすい人の特徴
大腸がんになりやすい人は、上記で述べたようなリスク要因を持っている人とされます。具体的には、以下の特徴を持つ人が大腸がんの発生危険性が高まると考えられます。
- ・喫煙者
- ・飲酒習慣がある人
- ・肥満の人
- ・肉食中心の欧米型食生活を送っている人
- ・大腸がんの家族歴がある人
大腸がんの治療方法
大腸がんの治療方法は、主に以下のものが挙げられます。
- ・内視鏡による切除
- ・外科手術
- ・抗がん剤治療
- ・放射線治療
- これらを組み合わせた集学的治療
治療の選択はステージによって異なります。
- ステージ0およびステージ1の多く: 内視鏡による治療が行われることが多いです。
- ステージ1の一部およびステージ2以降: 手術、抗がん剤治療、放射線治療、またはそれらを組み合わせた集学的治療が行われます。
大腸がんの検査方法
〇大腸内視鏡検査
大腸がんの検査方法は複数ありますが、それぞれにメリットとデメリットがあります。
メリット: 大腸がんを診断する上で最も適切な検査方法であり、同時に治療の手段にもなり得る(ポリープ切除など)。
デメリット: 下剤の服用、食事制限が必要であり、検査に多少の苦痛を伴う可能性がある。
〇便潜血検査
メリット: 検査の中で身体への負担が最も少ない。便潜血陽性の人の約半数程度でポリープ、2-3%でがんが見つかることがある。
デメリット: 他の検査に比べて検査の精度が劣る。実際にがんの人が便潜血検査を受けても、全員に異常が発見されるわけではない。
〇CT検査
目的: 大腸がんを見つける検査というよりは、ステージ(病期)を判定する目的で使われることが主です。
〇CTコログラフィー
大腸ポリープやがんを見つけることは可能ですが、大腸内視鏡に比べて精度が落ち、ポリープが見つかっても同時に治療ができず、結果的に内視鏡検査が必要になることがあります。放射線の被曝の問題もデメリットとして挙げられます。
〇PET-CT
CTと同様に、大腸の病期ステージ判定のために使われることがあります。小さなポリープやがんが見つかることもありますが、利便性に欠け、一般的な全身検査で行われることは稀で、大掛かりな人間ドック以外ではあまり実施されません。
〇注腸検査(バリウム造影)
かつて内視鏡が普及する前は主流の検査でしたが、現在は主に外科治療前の局在診断(がんの場所確認)目的で行われています。
〇大腸カプセル内視鏡
将来的には有望な検査とされていますが、現時点では下剤の服用が必要、内視鏡に比べて精度が劣る、同時に治療ができないといった課題があり、あまり普及は進んでいません。
大腸がんの早期発見は下北沢駅前きみじま消化器内科・内視鏡・肛門外科クリニックへ
大腸がんの早期発見は極めて重要です。日本では、大腸がんの罹患者数は男女合わせて第1位であり、死者数で見ると女性では第1位、男性では第2位と非常に多く、日本は諸外国と比較して罹患者数が増加しています。
これは、日本の大腸がん検診の主流である便潜血検査の受診率が決して高くないこと、そして「大腸ポリープを経てがんになる」という経路があるにも関わらず、ポリープを見つける予防治療という考えが日本に浸透していないことが原因であると個人的に考えています。
海外からは日本の高い医療技術を求めて大腸がんの早期発見に大切な内視鏡検査を受けに来る人もいます。近年の内視鏡機器は性能が非常に向上しており、例えば4Kの高画質で見られることや、視野角が広いこと(従来の140°に対し、170°)、さらにAIを搭載しているものもあります。これらの高性能な機器を、経験豊富で専門知識を持った医師が使用することで、精度の高い安全な検査が可能であり、苦痛も最小限に抑えられます。
早期発見のためには、積極的に内視鏡による検診を受けることが大切です。
また、軽い症状であっても不安がらずに受診していただきたいと強調されています。
内視鏡検査は「下剤がきつい」「検査が大変」という過去のイメージが高いですが、現在当院では複数の種類の下剤から選択可能であり、患者さんの希望があれば鎮静剤を使って苦痛を限りなく軽減した状態で検査が可能です。
当院では、20代から80歳まで幅広い年代の患者さんが検査を受けています。
元々外科医として、手術が必要な進行大腸がんの患者さんや、手術ができないほど進行した患者さんを数多く治療してきた経験から、検査を受けるきっかけが少ない現状を変えたいという思いがクリニックのポリシーとなっています。
外科医の手にかかる前の段階で見つけられる術があるにも関わらず、検査や受診のハードルが高いという思い込みで、結果的に患者さんにとってマイナスになっている状況を変えていきたいと考えています。
大腸がんは、早期に発見できれば基本的に命に関わることは非常に少ないため、とにかく症状がない状態でも定期的に検査を受けることが重要です。外科手術を避け、内視鏡で治療を完結できることの差は非常に大きく、患者さんのその後の食事や体力に大きく影響するため、なるべく早く見つけることが重要です。
下北沢で大腸カメラ検査をお考えの方は、下北沢駅前きみじま消化器内科・内視鏡・肛門外科クリニックまでお気軽にご相談ください。