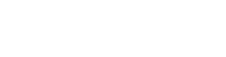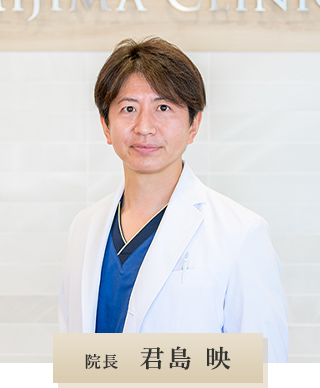胃がん
胃がんとは
胃がんは、胃の粘膜から発生する癌です。かつては日本を含む東アジアでピロリ菌感染率が高かったため、胃がんは国民病の一つとして認識されていました。
日本では、胃がんは依然として重要な癌の一つであり、最新のデータでは、癌患者の年間罹患者数において男女合わせると第3位、男性では第4位、女性でも第4位を占めています。
死亡者数においても、男女合わせて第4位、男性では第3位、女性では第5位と高い位置にあります。
しかし、近年では公衆衛生の改善やピロリ菌感染率の低下に伴い、胃がんの罹患者数や死者数は減少傾向にあります。
胃がんの症状
胃がんは、基本的に進行するまで症状が出ることは非常に稀です。そのため、早期のうちに癌を発見するためには、定期的な内視鏡検査が非常に重要です。
また、ピロリ菌感染の有無を一度きちんと検査しておくことも大切です。
症状が現れる胃がんのほとんどは進行した場合で、以下のような症状が認められます。
- 胃の不快感
- 痛み
- 違和感
- 吐き気や実際に吐いてしまう
- 食欲不振
- 体重減少
- 便が黒くなる(タール便)
胃がんのステージ
胃がんのステージは、ステージ1から4までの4段階で分類され、ステージ0は存在しません。ステージを決定する主な要素は以下の3つです。
- 浸潤度(病変の深さ): 癌が胃の壁にどれくらいの深さまで入り込んでいるか。
- リンパ節転移: 胃の周りのリンパ節や、遠く離れた全身のリンパ節に転移があるか。
- 遠隔転移: 肺、肝臓、腹膜などの胃以外の臓器に転移しているか。
ステージの概要は以下の通りです。
■胃がんの進行度分類
|
リンパ節転移 |
N0 転移なし |
N1 1-2個 |
N2 3-6個 |
N3a 7-15個 |
N3b 16個以上 |
|
T1a, T1b, M, SM 粘膜、粘膜下層に限局 |
IA |
IB |
IIA |
IIB |
IIB |
|
T2, MP 筋層に達している |
IB |
IIA |
IIB |
IIIA |
IIIA |
|
T3, SS 筋層をこえている |
IIA |
IIB |
IIIA |
IIIB |
IIIB |
|
T4a, SE 胃の表面に出ている |
IIB |
IIIA |
IIIB |
IIIC |
IIIC |
|
T4b, SI 胃の表面に出て、他の臓器にもがんが続いている |
IIIA |
IIIB |
IIIC |
IIIC |
IIIC |
|
肝、肺、腹膜、遠隔リンパ節などに転移している |
IV |
||||
(看護roo!より引用)
胃がんの原因
胃がんの主な原因は、胃の粘膜細胞が慢性炎症の結果、遺伝子変異を起こして発がんすることとされています。その中で、ヘリコバクター・ピロリ菌感染が大きく関与しています。
日本では過去にピロリ菌の感染率が高く、胃がんの主要な原因とされてきましたが、近年は感染率が低下し、徐々に減少傾向にあります。
その他に胃がんのリスク要因として、以下のものが挙げられます。
- タバコ
- 塩分の過剰摂取
- アルコール
- ストレス
- 刺激物
- 遺伝的素因
- 高齢の男性
何歳から胃がん検診を受けるべき?
一般的に、40歳以降から定期的に胃がん検診を受けることが推奨されます。特に、ピロリ菌感染と胃がん発生には密接な関係があるため、たとえ若い方であっても胃の症状がある場合は、内視鏡検査を受けて早期にピロリ菌を発見し、除菌することが胃がんの発生予防に繋がります。
胃がんの治療方法
胃がんの治療方法は、主に以下の3つが挙げられます。
- 内視鏡による切除
- 外科手術
- 抗がん剤治療
早期に発見された胃がんであれば、外科的に胃を切除することなく、内視鏡治療で治せる可能性が高いです。内視鏡治療は、癌が非常に浅い層にとどまっており、胃の外のリンパ節に転移している可能性が非常に少ない場合に適用され、内視鏡だけで治癒が期待できます。
一方、進行した胃がんに対しては、腹腔鏡下手術やロボット手術が普及しており、かつての開腹手術に比べて体への負担が少ない治療が主流となっています。
しかし、外科治療は胃そのものを切除する必要があるため、手術後に胃が小さくなり、食生活に注意が必要になるなど、身体への負担や生活の質の変化が大きいです。そのため、できる限り早期発見し、内視鏡で治療を完結させることが非常に重要だと考えられています。
胃がんの検査方法
胃がんの検査方法として、最も推奨されるのは内視鏡検査です。
〇内視鏡検査(胃カメラ検査):
近年の内視鏡は性能が向上しており、非常に微細な早期がんも発見することが可能になっています。カメラ自体の太さも細くなり、以前の内視鏡に比べて体への負担は限りなく減っています。
ピロリ菌感染者や萎縮性胃炎の方は、年に1回程度の内視鏡検査を受けることが望ましいとされています。それ以外の方でも、明確な定期検査期間は確立されていませんが、およそ2~3年に1度は検査を受けることが推奨されます。
経験豊富な医師が、高性能の内視鏡を使用することで、診断の精度、安全性、そして患者の苦痛を最小限に抑えることができます。
胃がんによる命を落とさないためには、いかに早く見つけるかが極めて重要であり、内視鏡検査がそのための最も有効な手段です。
〇バリウム検査:
かつては胃がん検診の主流でしたが、医学的にバリウム検査よりも内視鏡検査の方が優れていることが確立されています。
進行がんは見つかることが多いものの、早期がんの発見は内視鏡検査でないと非常に難しいのが現状です。
〇CT検査:
大腸がんの場合と同様に、胃がんを診断するというよりは、胃がんの病期(ステージ)を診断する目的で使われます。
胃がんの早期発見は下北沢駅前きみじま消化器内科・内視鏡・肛門外科クリニックへ
ピロリ菌感染の減少に伴い、胃がんの罹患率は減ってきていますが、それでも胃がんは未だに非常に重要な癌であり、男性では罹患者数・死亡者数ともに第4位以内、女性でも死亡者数が第5位を占めています。
2013年2月21日から、症状のない慢性胃炎に対するピロリ菌除菌療法が適用されて以来、約10年でピロリ菌除菌後の経過観察や、ピロリ菌がいない人における胃がん発生に関する研究が非常に進みました。
この進んだ知識を持って内視鏡検査を行うクリニックと、そうでないクリニックでは、その検査の意味合いが大きく異なります。
したがって、経験と知識をしっかり持ったクリニックでの検査を強くお勧めします。
胃がんは、早期に発見されれば基本的に命に関わることは非常に少ないです。
しかし、外科手術に至ると、術後に食事が思うように食べられなくなったり、体重が減って体力が落ちたりするなど、患者さんの生活の質に大きな影響を与えることがあります。
内視鏡治療で完結できる場合と外科手術が必要な場合では、その後の体の負担が非常に大きく異なるため、症状がない状態でも定期的に検査を受けることが極めて重要です。
健康診断で異常が指摘された場合や、軽い症状でも不安を感じずに受信していただきたいです。過去の内視鏡検査に対する「下剤が辛い」「検査が大変」といったイメージはありますが、現在は複数の下剤の種類が選べたり、患者さんの希望に応じて鎮静剤を使用することで苦痛を最小限に抑えて検査を受けることが可能です。
当院のようなクリニックでは、20代から80歳まで幅広い年代の患者様が検査を受けており、受診のハードルは決して高くありません。
多くの進行がん患者さんを治療してきた経験から、早期発見がいかに患者さんのその後の人生を大きく変えるかを痛感しており、「できる限り早く見つけましょう」というのが私たちのポリシーです。
少しでも心配な症状がある方は、下北沢駅前きみじま消化器内科・内視鏡・肛門外科クリニックまでお気軽にご相談ください。