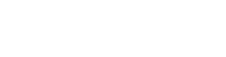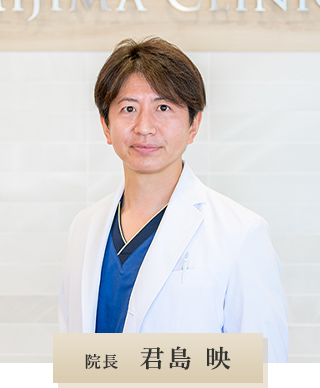血便について
 血便とは、文字通り便に血液が混じっている状態を意味していますが、一口に血便と言っても様々な原因があります。排便の際に便に血が混じっていることもあれば、肛門から血液が垂れている場合もあります。便が真っ黒になっている患者さんもいらっしゃいます。排便をすることで痛みが治まることもあれば、痛みが強まることもあります。特段の痛みを伴わないため、あまり気にされていない方もいらっしゃるようです。しかし、放置していると危険なケースもあります。血便がみられた場合、肛門の疾患によって起こることも多いのですが、大腸がんが潜んでいることもあるので、できるだけ早く医療機関を受診するようにしてください。
血便とは、文字通り便に血液が混じっている状態を意味していますが、一口に血便と言っても様々な原因があります。排便の際に便に血が混じっていることもあれば、肛門から血液が垂れている場合もあります。便が真っ黒になっている患者さんもいらっしゃいます。排便をすることで痛みが治まることもあれば、痛みが強まることもあります。特段の痛みを伴わないため、あまり気にされていない方もいらっしゃるようです。しかし、放置していると危険なケースもあります。血便がみられた場合、肛門の疾患によって起こることも多いのですが、大腸がんが潜んでいることもあるので、できるだけ早く医療機関を受診するようにしてください。
血便の主な原因疾患
痔核・裂肛
血便は、裂肛や痔核によって引き起こされるケースがよくあります。例えば、肛門の内側にある血管の流れが悪くなると、こぶ状の痔核ができてしまい、患部が腫れてきます。このような状態のときに排便すると、血便になりやすいです。とくに、排便時にいきむ、便秘が続いている、長時間同じ態勢をとっている、などの場合に発症しやすくなります。こうした痔疾患のときは、患者さんの状態を見極めたうえで手術療法や保存療法を行うので、血便も治まります。
大腸がん
大腸がんは、大腸の粘膜から発生する悪性腫瘍です。以前は欧米人に多く、日本人には比較的に少ないといわれていた時代もありました。しかし、現在は食生活の欧米化などによって非常に多くみられる悪性腫瘍で日本の2023年の臓器別がん死亡数の女性の1位、男性の2位で近年も増加傾向にあります。また、最近の日本では、大腸がんの若年化(50歳未満での発症)が増加傾向にあります。症状に関しては、発症初期の段階では痛みなどがほとんどないため、患者さんが自覚することは困難です。そのため、定期の健康診断で行う便潜血検査や、人間ドックでの大腸カメラで気づくことが大半です。とくに50歳以上の方は、大腸がんを発症するケースが多くなりますので、定期健診などを欠かさないようにしてください。大腸がんの主な症状は、血便、腹痛、便秘や下痢の繰り返し、体重減少、食欲不振、腹部膨満感、貧血などです。リスク因子としては、50歳以上、高カロリー摂取の食生活(高脂肪食、低繊維食、赤赤身肉、加工肉)、遺伝的要因(大腸がんの家族歴)、過量のアルコール、喫煙、炎症性腸疾患(クローン病や潰瘍性大腸炎)が挙げられます。
血便の見た目から考えられる疾患
| 血便の種類 | 見た目 | 出血箇所 | 疑われる疾患 |
|---|---|---|---|
| 鮮血便 | 鮮やかに赤い 真っ赤な血液が付着、または混じっている状態 |
肛門 直腸 |
など |
| 暗赤色便 | 変色した暗い赤色の便 | 大腸の奥の方 小腸 |
など |
| 黒色便 | タールのように黒っぽくてベタベタした感じの便 | 食道 胃 十二指腸 |
など |
血便とストレスの関係について
ストレスが直接的に血便の原因となることはありませんが、精神的な緊張などによって腸の働きが乱れ、下痢や便秘を引き起こすことがあります。過敏性腸症候群(IBS)では、強い下痢によって肛門が切れ、出血することがありますし、便秘タイプの場合には強くいきむことでいぼ痔を発症し、排便時の出血に気づくケースも多くあります。
腸の動きは自律神経によって調整されているため、ストレスの影響を受けやすく、便通異常とともに出血が起こることもあります。また、潰瘍性大腸炎やクローン病といった炎症性腸疾患では、ストレスが症状を悪化させ、血便が見られることがあります。血便は、軽度な肛門の異常から重篤な疾患まで幅広い可能性があるため、見過ごさず早めに消化器内科を受診することが大切です。
血便がある場合の検査と治療
 血便が見られた際には、出血している部位をある程度特定できれば、必要最小限の検査で原因を突き止められる可能性があります。例えば、黒っぽいタール便が出た場合は、上部消化管(食道・胃・十二指腸など)からの出血が疑われ、胃カメラ検査が有効です。また、大腸奥深くや小腸での出血も黒っぽい便になることがあるため胃カメラにて異常を認めない場合は、大腸カメラでの確認も必要となる可能性があります。一方で、鮮やかな赤色の血便は、肛門や大腸からの出血が考えられるため、大腸カメラ検査での確認が適しています。
血便が見られた際には、出血している部位をある程度特定できれば、必要最小限の検査で原因を突き止められる可能性があります。例えば、黒っぽいタール便が出た場合は、上部消化管(食道・胃・十二指腸など)からの出血が疑われ、胃カメラ検査が有効です。また、大腸奥深くや小腸での出血も黒っぽい便になることがあるため胃カメラにて異常を認めない場合は、大腸カメラでの確認も必要となる可能性があります。一方で、鮮やかな赤色の血便は、肛門や大腸からの出血が考えられるため、大腸カメラ検査での確認が適しています。
血便が出たときは、落ち着いて便の色・性状・量などをよく観察し、その情報を医師に伝えることが早期診断の手助けとなります。可能であればスマートフォンなどで便の写真を撮っておくと、より詳細な情報提供につながります。
診察では、血便の状態のほかに、最初に気づいた時期、発生頻度、伴う症状、既往歴、現在使用している薬などについて詳しくお伺いします。特定の薬が副作用として出血を引き起こすこともあるため、お薬手帳や服用中の薬を持参いただくことが望ましいです。
原因が判明したあとは、それぞれの病態に応じた治療を行います。当院では消化器科に加えて肛門疾患にも対応しており、血便の原因に合わせた的確な治療が可能です。また、必要に応じて連携する大学病院などの専門機関をご紹介し、迅速に高度な医療を受けられる体制を整えています。