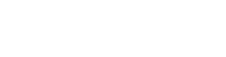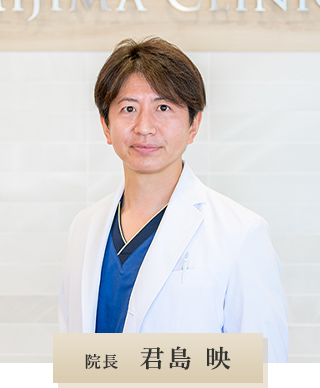日帰りで行える大腸ポリープ切除

大腸内視鏡検査では、大腸全体の粘膜を詳しく観察し、必要があれば組織を採取して病理検査を行うことで確定診断が可能です。また、検査中に発見されたポリープに対しては、その場で切除治療が行えるため、迅速な対応とともに、後日検査を受けなければならないようなことが回避できます。特に、前がん病変のポリープを発見した場合、同様に、検査に並行して同時に日帰りで手術を行うことができる点が大きな利点です。
これにより、入院を避け、別日での手術の必要もなくなります。事前に必要な食事制限や下剤服用も1回で済むため、患者さんへの負担が軽減されます。
なお、ポリープが大きく広範な切除が必要な場合や粘膜の下層まで病変が及んでいるであろうポリープに関しましては、入院での手術が必要となる場合もあります。その際には、内視鏡治療に特化した適切な医療機関をご紹介し、スムーズに治療が受けられるようサポートいたします。
大腸ポリープについて
大腸ポリープは、大腸の粘膜にできる卵球形・イボ状のできものの総称です。大部分のポリープは良性ですが、放置しておくとがんに変わる可能性がある「腺腫」と呼ばれるポリープや腺腫に比べてがんに変わる可能性は低いもののその可能性のある「鋸歯状腺腫」があります。これらの腺腫は大きさによって確率は異なるもののがんになる可能性があることから前がん病変とされ、大きさは小さくても早期に発見し切除することで将来の大腸がん予防につながります。また、大腸内視鏡を用いて早期の大腸がんを発見し、切除することで治療可能な場合もあります。
内視鏡を使った治療は非常に有効ですが、ポリープの状態や大きさに応じて、どの切除方法が最適かを慎重に判断することが重要です。当院では、日本消化器内視鏡学会認定の専門医である院長と専門医を持った院長が信頼する経験豊富な医師(女医も在籍)で内視鏡検査を行っており、安心してご相談いただけます。
大腸ポリープの症状について
大腸ポリープのほとんどは自覚症状を引き起こしませんが、まれに肛門に近い場所に大きなポリープや茎が長いポリープができることがあります。この場合、異物感や脱出感など、内痔核に似た症状が現れることがあります。しかし、ポリープ自体が血便や痛みを引き起こすことはほとんどありません。
便潜血検査で陽性となり、大腸内視鏡検査を受けた際に約30〜50%の確率で大腸ポリープが発見されることがありますが、それ以外にも検診や他の疾患の疑いで偶然に内視鏡検査を受けた際に見つかることが多いです。
大腸ポリープを早期に発見するためには、症状が現れる前に定期的に大腸内視鏡検査を受けることが非常に重要です。
大腸ポリープと大腸がんの関係
大腸ポリープががんに進行するには、通常、長い時間がかかります。状況によっては何十年もかかることもあります。年齢や生活習慣・遺伝の影響によって、遺伝子に異常が起こりやすいかどうかが変わりますが、長期間をかけて細胞に異常が蓄積し、その一部ががん化して増殖する過程が進みます。ポリープが大きくなると、異型度が高くなり、正常な状態から大きく外れるようになります。
ポリープの大きさとがん化のリスクには明確な関連があり、10mm未満のポリープでは約15%、10mm以上20mm未満では約39%、20mm以上では約65.9%ががん化する可能性があります。つまり、ポリープの大きさが大きくなるほど、がん化するリスクが高くなります。
早期の大腸がんは内視鏡による治療が可能ですが、進行した場合、外科的手術が必要となり、さらに進行すると転移のリスクが高まり、命に関わったり治療の負担が大きくなります。早期発見と治療の重要性を理解し、予防や早期治療の機会を逃さないことが、将来の健康維持や生活の質(QOL)を守るために非常に大切です。
内視鏡で治療できる大腸がん
 大腸がんの治療といえば手術が一般的に思い浮かびますが、早期の大腸がんに関しては、内視鏡による治療で完治する場合が多くなっています。内視鏡治療は心身への負担が少なく、回復も早いという利点がありますが、この治療が可能かどうかはがんの進行度により決まります。
大腸がんの治療といえば手術が一般的に思い浮かびますが、早期の大腸がんに関しては、内視鏡による治療で完治する場合が多くなっています。内視鏡治療は心身への負担が少なく、回復も早いという利点がありますが、この治療が可能かどうかはがんの進行度により決まります。
がん細胞が進行すると、周囲の組織に浸潤し、さらに進行すると血液やリンパ管を通じて大腸の周りのリンパ節や他の臓器に転移することがあります。内視鏡での治療が難しくなり、外科手術が必要となるのは、大腸に存在するがんのみを完全に取り除くだけでは不十分で、浸潤や転移の可能性がある組織も一緒に除去する必要があるからです。浸潤や転移した小さながん細胞は内視鏡検査での確認は困難で、周囲の健常な組織の一部を余分に含めて切除することが求められます。大腸がんでは、通常、がんとそのがんから約10㎝離れた場所まで含めて一括で切除し、その周囲のリンパ組織にも小さながん細胞が潜んでいる可能性があるため、これも考慮して外科切除が行われます。
内視鏡で切除が可能な大腸がんは、早期のものに限られています。精密検査で得られた診断結果をもとに多くの研究データを考慮して、大腸の壁奥深くやリンパ組織、他の臓器に浸潤や転移していないことが確認されているものが対象です。大腸の粘膜にとどまっている早期大腸がんであれば、内視鏡による切除で治療が完了します。また、がんが粘膜のすぐ下の粘膜下層にまで進行している場合でも、内視鏡で切除することが可能です。ただし、粘膜下層でも深い層まで進行していたことが切除した後の組織検査の結果で判明された場合、大腸周囲のリンパ節にがんが転移している可能性が少し残るため、リスクを考慮した対応が必要です。具体的にはリンパ節に転移している可能性が約10%程度弱とされるため、追加で外科手術での切除を選ぶか、内視鏡での治療後に慎重にCT検査などの画像診断を含めて経過観察を行うかを選択することになります。
このような選択肢に関しては、主治医と十分に相談し、リスクやメリットを理解した上で、最も適した治療法を選ぶことが大切です。
内視鏡で治療できる大腸がん

大腸がんの治療といえば手術が一般的に思い浮かびますが、早期の大腸がんに関しては、内視鏡による治療で完治する場合が多くなっています。内視鏡治療は心身への負担が少なく、回復も早いという利点がありますが、この治療が可能かどうかはがんの進行度により決まります。
がん細胞が進行すると、周囲の組織に浸潤し、さらに進行すると血液やリンパ管を通じて大腸の周りのリンパ節や他の臓器に転移することがあります。内視鏡での治療が難しくなり、外科手術が必要となるのは、大腸に存在するがんのみを完全に取り除くだけでは不十分で、浸潤や転移の可能性がある組織も一緒に除去する必要があるからです。浸潤や転移した小さながん細胞は内視鏡検査での確認は困難で、周囲の健常な組織の一部を余分に含めて切除することが求められます。大腸がんでは、通常、がんとそのがんから約10㎝離れた場所まで含めて一括で切除し、その周囲のリンパ組織にも小さながん細胞が潜んでいる可能性があるため、これも考慮して外科切除が行われます。
内視鏡で切除が可能な大腸がんは、早期のものに限られています。精密検査で得られた診断結果をもとに多くの研究データを考慮して、大腸の壁奥深くやリンパ組織、他の臓器に浸潤や転移していないことが確認されているものが対象です。大腸の粘膜にとどまっている早期大腸がんであれば、内視鏡による切除で治療が完了します。また、がんが粘膜のすぐ下の粘膜下層にまで進行している場合でも、内視鏡で切除することが可能です。ただし、粘膜下層でも深い層まで進行していたことが切除した後の組織検査の結果で判明された場合、大腸周囲のリンパ節にがんが転移している可能性が少し残るため、リスクを考慮した対応が必要です。具体的にはリンパ節に転移している可能性が約10%程度弱とされるため、追加で外科手術での切除を選ぶか、内視鏡での治療後に慎重にCT検査などの画像診断を含めて経過観察を行うかを選択することになります。
このような選択肢に関しては、主治医と十分に相談し、リスクやメリットを理解した上で、最も適した治療法を選ぶことが大切です。
大腸カメラ検査について

大腸カメラ検査では、ポリープの大きさや色、形状、血管の有無や太さ、表面の状態、周囲の毛細血管の分布など、さまざまな特徴を詳細に観察し、診断を行います。その上で、病理検査のために組織を採取するか、またはその場で日帰り手術による切除を行うかを判断します。切除が必要な場合は、ポリープの状態に応じて最適な方法を慎重に選択し治療を行います。
当院では、最新の内視鏡システムとスコープ、大学病院などで使用している内視鏡処置具を使用して高度な検査・治療を実施しています。また、日本消化器内視鏡学会認定の専門医である院長が、丁寧な検査・診断を行い、安全かつ精度の高い切除を提供しています。これにより、患者さんにとって安全で信頼性の高い治療を実現しています。