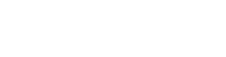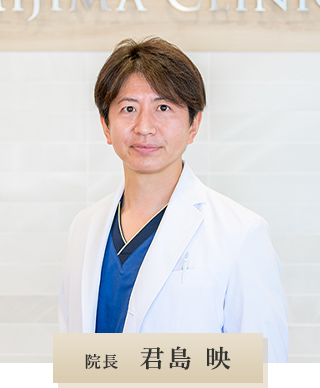下痢について
 健康な便の水分量は60~70%程度です。下痢とは、この水分量が異常に多くなっている状態を意味しています。具体的には、便の水分量が80%になると「軟便」、90%以上では「水様便」と診断されます。ご自身の排便を確認し、軟便になっている、あるいは液状になっているときは、必要に応じて医療機関を受診するようにしてください。
健康な便の水分量は60~70%程度です。下痢とは、この水分量が異常に多くなっている状態を意味しています。具体的には、便の水分量が80%になると「軟便」、90%以上では「水様便」と診断されます。ご自身の排便を確認し、軟便になっている、あるいは液状になっているときは、必要に応じて医療機関を受診するようにしてください。
このようなときはご受診ください
- 長期にわたって下痢が続いている
- いったん収まっても、再び下痢になることがある
- 腹痛を伴っている
- 高熱を伴っている
- 何度も吐いてしまった、吐き気がする
- 同じ食事をした人が下痢をしている
- 下痢便に血が混じっている
など
下痢のタイプ
下痢の中には、分泌性下痢、浸透圧性下痢、運動亢進性下痢などのタイプがあります。このうち分泌性下痢は、食中毒など細菌への感染によって起こります。細菌感染以外でも、食物アレルギー、薬の副作用などにより、腸管内の分泌液が過剰に出てしまい、下痢となることがあります。浸透圧性下痢は、腸の水分吸収が不十分なときに起こります。
例えば、水分を引き付ける浸透圧を高める食べ物の摂り過ぎや、マグネシウム含有の下剤やサプリメントの影響で水分が上手く吸収されず、下痢となってしまいます。運動亢進性下痢は、暴飲暴食やストレスによる過剰な腸の動きが関係しています。ストレスなどで自律神経のバランスが崩れると、腸の活動が過剰になり、便の通過スピードが速くなって水分の吸収が十分に行われなくなります。
こうした下痢は一般的に4週間以内に治まる急性下痢であることがほとんどですが、それ以上続くこともあります。その場合は、慢性下痢と呼ばれます。慢性下痢の原因としては、ストレスなどが原因の過敏性腸症候群、大腸の粘膜に慢性的な炎症が起きることで発症する潰瘍性大腸炎、小腸・大腸クローン病、腸の中にできた大腸がんや大きい大腸ポリープなどが考えられます。
下痢の原因
下痢にはさまざまな原因があります。主なものには以下が挙げられます
食あたり・細菌感染
生ものや調理後に時間が経過した料理を食べた際、食あたりや細菌に感染することで下痢が起こることがあります。
食物アレルギー
小麦や魚介類など、特定の食物にアレルギー反応を起こすと、腸内で過剰な分泌物が出て、下痢が引き起こされることがあります。
薬の副作用
解熱鎮痛剤などの薬が腸に影響を与え、腸粘膜を傷つけて下痢を引き起こす場合があります。
ストレス・暴飲暴食
冷えやストレス、暴飲暴食などが原因で、自律神経が乱れ、腸の動きが活発になりすぎることがあります。その結果、腸内で十分に水分を吸収できず、便がゆるくなることがあります。
腸の炎症や腫瘍
腸自体に炎症や腫瘍がある場合も、下痢を引き起こす原因になります。
また、下痢が1ヶ月以上続くと「慢性下痢」と呼ばれ、神経性の問題や重大な病気の兆候である可能性もあります。長引く場合は、早めに病院で相談することをお勧めします。
過敏性腸症候群
患者さんが下痢などの消化器症状を訴えている場合には、原因を特定するための検査を行います。しかし、様々な検査をしても炎症や潰瘍などの病変が見つからないことがあります。そのようなときは、過敏性腸症候群の可能性があります。偏食や過食を繰り返している方、ストレスが溜まりやすい方、腸内細菌のバランスが良くない方によくみられます。大腸は第2の脳とも呼ばれストレスなどの精神的な影響を受けやすい器官なので、下痢などの便通異常を起こすことがよくあります。
潰瘍性大腸炎
潰瘍性大腸炎は、大腸の粘膜に炎症が起こる病気です。初期の段階では肛門近くの直腸から炎症が起こり、だんだんと肛門より遠い結腸に向かって病状が広がっていきます。炎症は進行するとただれていき、潰瘍になっていきます。この病気は一度発症してしまうと、良くなることもあれば悪くなることもあるといった状態を繰り返していきます。下痢や血便などの症状も繰り返されます。
下痢の検査
下痢が続く場合、過去3ヶ月以内に1ヶ月あたり腹痛が3日以上続いたり、腹部に不快感を感じることがあったりする場合、以下の診断基準に基づいて検査を行います。
- 排便によって症状が和らぐか
- 症状によって排便回数が変化するか
- 便の形状に変化があるか
 主な検査には、大腸カメラ検査、大腸造影検査、血液検査、尿検査、便検査があります。これらの検査で異常がある部位を特定します。また、必要に応じて腹部超音波検査を行い、悪性腫瘍や炎症、寄生虫、細菌の有無を調べます。
主な検査には、大腸カメラ検査、大腸造影検査、血液検査、尿検査、便検査があります。これらの検査で異常がある部位を特定します。また、必要に応じて腹部超音波検査を行い、悪性腫瘍や炎症、寄生虫、細菌の有無を調べます。
下痢の治療法
 下痢は一時的な症状から慢性的な症状まで様々です。激しい腹痛や発熱、嘔吐を伴う場合は直ちに病院で受診されることをおすすめします。その他にも、長期間の下痢や血便、便の色が赤・黒・白の場合も、早めに医師に相談しましょう。
下痢は一時的な症状から慢性的な症状まで様々です。激しい腹痛や発熱、嘔吐を伴う場合は直ちに病院で受診されることをおすすめします。その他にも、長期間の下痢や血便、便の色が赤・黒・白の場合も、早めに医師に相談しましょう。
主な治療法として、腸の働きを抑えるための下痢止め(腸の運動を止めるタイプや炎症を緩和させることによって腸の運動を抑えるタイプなど)、有害な細菌を殺菌するための抗生剤が使用されます。また、荒れた腸内の粘膜を保護したり、腸内の水分を吸着させるための薬を処方することも多いです。その上で腸内環境を整えるための整腸剤も処方します。
潰瘍性大腸炎やクローン病の場合、根治的な治療法が現在まだ発見されていません。ただし、症状を軽減するための薬物治療を行い、炎症を和らげることは可能です。
大腸がんの場合は、早期発見の場合は内視鏡を使って腫瘍を切除することもありますが、進行具合によっては外科手術や放射線治療、抗癌剤治療を行うこともあります。
原因が見つからない場合、ストレスや精神的な影響による「過敏性腸症候群」と診断されることも増えてきています。